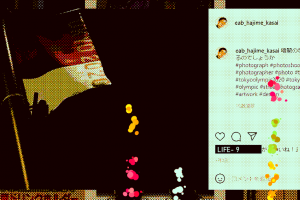(by 葛西祝)
その音楽は “文化的荒涼”のただ中にて、Twitterのタイムラインで称賛された。
オリエンタリズムのクリシェに塗れた演目が終わり、選手入場のイベントが始まる。噂された『ドラゴンクエスト』序曲が鳴り響き、各国から選手が競技場へ歩み始めた。オーケストラはやがて『ファイナルファンタジー』の勝利テーマへ変わり、さまざまなVGMへメドレーは遷移してゆく。だけど実況は、この光景を前にただの一言も何のゲームの楽曲であるか解説しなかった。抽象的な表現であるコンテンポラリーダンスでさえも何を象徴するかを親切に(無粋にも)説明していたはずなのに。NHKの放送ガイドラインに「商品名を挙げない」ルールがあるのはわかった。しかし、作曲者の名前を挙げることもなかった。
荒涼とした文化状況下でVGMが演奏されたことを純粋に喜べるほど自分は無垢ではなく、無知でもない。自分は普段、ゲームメディアでテキストを書くことが主な立場だが、新国立競技場で鳴り響くビデオゲームミュージック(VGM)の光景は遠い国のことみたいに感じられた。
1. 文化的荒涼について
文化的荒涼とは何かって?
文化的荒涼とは、その文化を守る意志や、歴史的に意義あるものと解釈するかの営為がまるでない事である。個人や社会がある文化を血肉として、反映していく営為がまるで見えなくなっていったことも指している。その営為がないまま、漠然と文化が取り扱われる空疎さのすべてである。
具体的な例を挙げよう。ちょうど自分が文化的荒涼について考え込んだ出来事がある。
それは2020年11月2日の国会のニュースだった。衆院予算委員会にて野党側の質問に対し、菅義偉首相が「私も『全集中の呼吸』で答弁させていただく」と返したという。
自分はその内容が理解できなかった。一体いつ彼が『鬼滅の刃』を好んでいたのか? 仮に読んでいたとして、何を観ていたのか? 老政治家が作中の物語の解釈や理解より技を挙げた理由は? 官僚が答弁を書いたとするなら、首相の何を演出したかったのか?
『鬼滅の刃』は知ってのとおり、爆発的なヒットを記録し、映画も数百億を稼ぎだす収益を上げるコンテンツである。だが物語を読み解けば、極めて酷薄な現実の中で数世代に及ぶ復讐や怨恨、呪いの連鎖を断ち切り、未来に繋げていくかが描かれたものでもある。
しかし答弁から、首相が本作を読み込んだ形跡を見出すことは難しかった。菅総理が竈門炭治郎はじめ鬼殺隊たちの如く、政界に蔓延する呪いを断ち切る意志までもって本作に触れたとはとても思えない。莫大な利益を生み出すコンテンツへ、浅ましくすり寄った以上のものを感じられなかった。
ある時から国内の政治家に文化的教養を感じることが無くなった。教養を感じさせたエピソードも、いま自分が覚えている範囲では2006年の小沢一郎くらいだ。彼がまだ民主党にいた2006年のことだ。彼は民主党代表選の政権演説にて、ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画『山猫』を引用していた。
『山猫』はヴィスコンティの代表作のひとつであり、19世紀のイタリア統一戦争を舞台とした映画である。イタリア貴族の没落を描くとともに時代の変貌を描く内容だ。当時の小沢氏が自らの政治家としてのイメージを変えることに本作を重ね合わせ、引用したという。少なくとも本作を掘り下げ、血肉とし、演説に使った理由はわかる。
だが菅総理が『鬼滅の刃』をどれだけの意図で観ていたというのか? 『鬼滅の刃』が本質的に持っている物語性が彼自身の考えや意志にどれだけ直結しているというのか?
麻生太郎財務大臣が首相を務めたころからだろうか? ある時期から、ゲームからアニメ、漫画のように商業的な成果を上げたポピュラーカルチャーを、自身への支持を取り付ける触媒のようにしているケースが増えた。
そんな文化的荒涼を、自分はこの10年ほどじわじわと感じてきた。長らく見えない亡霊のように存在していたそれは、東京五輪の開会式によって具体的な風景として目の前に現れることになる。
2. 五輪型キャンセルカルチャーによる荒涼
文化的荒涼の風景は、単に公の側の文化へのすり寄りだけでは生まれない。複数の要因が絡み合うことで拡大していったと思う。
こと東京五輪においては、運営側内部の混乱、外部からのクレームによって、クリエイターへの批判や責任に収斂されることで、さらに文化的荒涼が広がってゆく。
東京五輪が今日の開催までに起こしたスキャンダルを振り返ると、その多くが実質的にクリエイターが矢面に立たされることになってしまったと思う。ざっと振り返ってみてもデザイン、音楽、演劇(もしくは広義の演芸、お笑い)などのジャンルだ。
それらの分野のクリエイターが、五輪開催反対という意志やインターネットの愉快犯といったものが絡みあう、けた外れに強力なクレームによって今日の地位を追われ、文化的荒涼を拡大させてきた。このことはキャンセルカルチャーという用語で評されることもあるが、もともとの定義を加味し、以下、本テキストでは便宜的に「五輪型キャンセルカルチャー」と明記する。
「有名デザイナーのロゴのパクリ」、「障害者への虐待」や「ホロコーストへの揶揄」という、一見すると反論しにくい根拠によって世論が形成され、結果としてクリエイター個人が強烈な糾弾に晒されることになった。
しかし今回話題としたいのは、事態の多くがいかに、結果的にクリエイター個人の責任へと収斂する形になり続けてしまったかである。このことは様々なジャンルのクリエイティブの今後に、深刻な禍根を残したと思う。
あらためて、当初の東京五輪のエンブレムデザインを担当したグラフィックデザイナーの佐野研二郎氏の問題を振り返ろう。
2015年に採用された佐野氏のデザインは、1964年の東京五輪に採用された亀倉雄策氏のエンブレムを再解釈する明確なコンセプトがあった。エンブレムには全体のシルエットのほか、右上のアクセントに置かれた日の丸から亀倉デザインがうかがえるようにしている。2度目の五輪開催までの56年間を象徴する意図も感じられるし、現代にリミックスされた五輪を見せるということだったのだろう。
だが過去をリミックスするコンセプトは、盗作スキャンダルによって一転する。
ベルギーのデザイナー、オリビエ・ドビ氏が、自身のデザインした劇場ロゴに似ているとして提訴。当初はIOCや組織委員会側も問題とせず、佐野氏の案を守る方向だった。しかしオリジネイターだというデザイナーの提訴や、この問題を静観する委員会側への反発か、五輪型キャンセルカルチャーは佐野氏への追求を加熱させる。
五輪型キャンセルカルチャーは、過去にネット愉快犯がアニメや漫画やJPOPなどで鍛え上げた盗作批判の技術の粋を結集させる。佐野氏案のエンブレムだけではなく過去の仕事にさえも盗作の跡を探し、反論の隙を作らせない世論を形成した。この事態に対する、同業者からのデザインにおけるクリエイティブの本質論もキャンセルの大波にかき消された。
その結果、佐野氏の会社には膨大な誹謗中傷のメールや悪戯が行われ、スタッフや家族を守るという判断から、彼自身がエンブレムを取り下げるという形となってしまったのである。
組織委員会側は本件を問題ないとし、佐野氏への処分を行わなかったのだと思うが、本件の問題を解消する説得力ある根拠を提示したアナウンスによって五輪型キャンセルカルチャーを鎮静化させることはできなかった。
結局エンブレム問題は、当初のオリビエ・ドビ氏の提訴が妥当かどうかの正規の判断を待たず、クリエイター自身が事実上辞退するかたちとなり、「どうあれ引きずり下ろした」結果に終わる。このことで五輪型キャンセルカルチャーという手法が大きな成功体験を得てしまい、いまに至るも無批判で、どうすればいいかわからないままだ。
いまエンブレム問題を振り返れば、この問題以降、各ジャンルがスキャンダルなどによって当初の案が棄却された後の代案として、保守的なオリエンタリズムに転じる皮肉な状況を先行してしまっていた。
佐野氏が取り下げた後、現在の五輪ロゴに野老朝雄氏のデザインが採用された。佐野氏と同じく亀倉デザインをリファレンスしたものの、江戸時代の市松模様をモチーフにしたものだ。それは誰からも反感を買わないオリエンタリズムによって収めたものだった。
それから5年後の現在、事態はある意味で反復される。
3. 運営側の判断による荒涼
続いて小山田圭吾氏・小林賢太郎氏の問題に入る。本テキストは当然ながら、小山田氏が過去に行った障害者への虐待を加担する行為はとうてい許されないし、お笑いとして何らかの根拠もなくホロコーストを揶揄することも許されないという前提である。
時間が経ったいま、まったく腑に落ちないのは、「そのポジションを外す経緯は、本当に義憤通りの、正当な手続きを取ったと言えたのか?」だ。
組織委員会側が扱いたいはずの文化ジャンルが、五輪型キャンセルカルチャーに押し流され、委員会側が責任を回避するかたちで、なし崩しのようにクリエイターを切り捨てる結末になったように映る。
小山田氏に関しては過去20年以上、インターネットで断続的に山崎洋一郎氏・村上清氏による当該インタビューが蒸し返されてきた。その間、当事者たちはこのことについて正式なアナウンスをしなかった。しかしパラリンピックに彼が起用されたと発表後、例のインタビューが再び注目され、五輪型キャンセルカルチャーに狙い撃たれることになる。
その後の顛末は知ってのとおりだ。「障害者を虐待した人間がパラリンピックの演出に関わることはありえない」という覆しがたい根拠を形成。組織委員会側はそれでも彼を残す判断だったが、小山田氏は五輪型キャンセルカルチャーに押されるかたちで、組織委員会に辞任を申し出る形となった。
小山田氏が辞任するまでの経緯の覆し辛さの一方、続く小林氏の解任には五輪型キャンセルカルチャーの無批判性が気にかかるものとなった。彼の解任までの経緯は、その義憤通りの正当な経緯であるか、背景や組織委員会側の決定を見るに疑問を抱くものだったと思う。
イエロージャーナリズムの中でも極端な雑誌である実話BUNKAタブーのアカウントが、当該ホロコーストの揶揄を扱ったというらしいコントの一部を切り取った動画を投稿。コントの中で、あくまで小林氏本人の小山田氏の辞任によって加熱した流れで、五輪反対派までもスキャンダル誌による戦略的な投稿を加味せずにシェアする事態が発生した。
スキャンダラスを狙う愉快犯の悪意だろうが、五輪開催をなんとしても止めたい人々がそこに乗りかかり、情報の出どころややり口を精査することのないまま世論を形成した。普段BUNKAタブーなど歯牙にもかけないはずの、ポピュラーカルチャーを追うライターや編集などが義憤によってリツイートする光景は、五輪キャンセルカルチャーが何たるかを象徴していたと言っていい。
それはさらに驚くべき事態を引き起こす。SNSにて、親イスラエルである中山泰秀防衛副大臣に事態を報告するアカウントが現れる。事態を把握した中山氏はサイモン・ヴィーゼンタール・センターに連絡。同じころ、ジャーナリストの高橋浩佑氏がYahooに今回の事態について記事化する。すさまじいスピードで組織委員会は小林氏の解任を発表した。
しかしこの問題が組織委員会を通してからの判断ではなく、中山氏の動きなど外的な経緯によって、なし崩しのように解任の結論を下したことは疑問視された。
さらに開会式では組織委員会側の処置も問題とされる。結局小林氏の案が使われるのだが、彼のクレジットだけが外される処置が取られたのである。このことはクリエイターを震撼させる。
デザインライター/キュレーターの角尾舞氏は以下のように発言した。「最後まで彼の仕事として見せるのか、全く別の案にするかの二択のはず」、「それでも彼のディレクションした演出を使うならば、責任者が彼を守ったうえで、世に出す判断をすべき」、「こんな前例を国レベルに作られてしまったら、日本でフリーランスのクリエイターでいるリスク、高すぎない……?」
4. 社会をないものとしたクリエイティブの荒涼
90年代に頭角を現し、当時はポピュラーカルチャー界隈で活躍してきた小山田氏や小林氏が2021年の現在、国家イベントに関わり、失脚した顛末は単なるスキャンダルには終わらなかった。彼らと同じ時代にポピュラーカルチャーを追いかけてきた、クリエイターから批評家などに今回の事態は深刻なダメージを与えた。
90年代から今までに、まるで政治的な現実も、社会もないものとして露悪的に振舞ってきたことをなぜ肯定してきてしまったのか……? 自分は本連載で以前、「かつて平成ではノンポリティカルであることが問題ない時代だった、今ではそうではない」ということを書いたが、まさしくそうしたスタンスだった人々が一斉に自己批判するように過去を振り返っていった。
爆笑問題の太田光は、サンデージャポンや自身のラジオにて、小山田氏の問題について90年代の当時、全体の環境が問題だったことを振り返った。小山田氏の露悪的なインタビューが世に流通する背景となった、90年代のサブカルチャーに関わった人々も、みな30年近く昔の状況について問い正し直した。「ポスト・サブカル焼け跡派」などの著作のある、テキストユニットTVODは、かねてからコーネリアスの音楽を好んでいたこともあり今回の小山田問題について自己言及する対談を残した。
小林氏の問題では、当事者であるユダヤ人の方からも意見が出ている。Noah Oskow氏のテキストは、かつてからのノンポリティカルであり続けた表現の問題を端的に指摘している。「当時(または今日でも)、ユダヤ人が日本でお笑い番組を見るとは誰も想像していなかったのだ。小林さんの考える範囲では、生きているユダヤ人は存在すらしていなかったのかもしれない」という言葉は、平成(あるいは昭和まで遡っても)通底している問題のすべてだろう。
その表現の外側に社会が存在していることを想定していない。「政治的ではないことも、政治的である」という言説があり、これは正しいと思う。だけどすぐにわかりにくいという人も多いと思う。
では言い換えるとして「ある表現はそのまま社会に直結している」とすればどうだろうか? あらゆる表現が放たれたその先には目の前のオーディエンスだけではなく、多彩な立場やアイデンティティを持つ人々が存在していると想像するということ。そのことの欠落が、ついに今日問われることとなった。
90年代からいままでは表現は、「その先にある社会や現実を欠落させたなかで、どこまで表現のピュアネスさがありうるのか?」を試し続けた時代だったと思う。ある意味で社会を切り捨てて表現を追求する事は真理だったかもしれない。しかし今現在、そのスタンスに限界があることを突きつけている。
そうしたピュアネスさがグロテスクへと反転するのが、まさしく開会式でVGMが流れた瞬間だった。
5. ピュアネスさがグロテスクへと反転する荒涼
開会式の選手入場にてVGMのメドレーは、もしゲームクラスタで、ここまでにまとめたような他ジャンルの文化状況をチェックしていなければ、荒涼を感じることもなかっただろう。実質的にサプライズだったこともあり、ざっくりと開会式を観ていた人にとって予想外の嬉しさがあったのかもしれない。
しかし自分には、ドラゴンクエストの序曲は虚しく聴こえた。政府側、組織委員会側、そして五輪型キャンセルカルチャーの内実や、そもそも社会が欠落していたクリエイターの起用と言ったすべての要素が揃うことによる、文化的荒涼が明らかな中で何が嬉しいのか。
序曲を聴きながら、すぎやまこういち氏のことを思い出していた。氏が南京虐殺を否定する発言を残したり、LGBTQ+への反対を口にしたりしても、五輪型キャンセルカルチャーが加熱する要因にはなりにくかった構図について思いをはせた。
キャンセルが猛威を増すコアとなる、インターネットベースでの義憤……いやもしかしたら何の感情もない愉快犯が襲撃するポイントを、すぎやま氏の背景はことごとくかわすことになる。
五輪型キャンセルカルチャーのコアとなるインターネット世論には、中国やフェミニズムへの蔑視がむしろ多く、ゆえにすぎやま氏には小山田氏のような強烈なキャンセルが発生しなかったように思う。(「いじめ」や「ホロコースト」と比べても、批判への参加しやすさはまるで違うだろう。)なによりも開催まで序曲の使用は公式には発表されず、あくまで事前の噂程度に収まっていたのも大きいだろう。
もうひとつ気になったのは「本当にこれはビデオゲーム(の音楽)文化を認めてのことなのか……?」ということである。開会式で引っかかったのは、作曲者の名前が実況されることもなく音楽が流れ続けたことだ。あとで作曲者に今回の音楽を使うという連絡なく使用されたことも知り、違和感はより増していった。
漠然と20代~40代のゲーマーが触れてきたVGMのメドレーが各国の選手たちの入場に合わせて流れる風景は、決定的なところでVGMの文化がこのイベントのなかで血肉になったものとして昇華されたとは思えなかった。
後の週刊文春が明らかにした五輪開会式の案の変遷によれば、当初は任天堂の参加も予定されており、宮本茂氏も大きく関わるつもりだったとのことだ。リオ五輪の閉幕式で大きくマリオがフィーチャーされたのは、開会式の伏線であったともいえるのだが、現実には当初のMIKIKO氏の案が頓挫したことでそれも無くなった。
やはりビデオゲームも政治や組織委員会側、電通側内部の事情によって、その文化的な側面を削られた状態で今日の開会式に至ったとのことだ。その他、いくつかの案も棄却されており、その代わりに都知事との関係で火消しの演出みたいな空疎なオリエンタリズムが入ることとなった。
ゆえに自分には「今回の開会式でVGMの社会的立場が上がった」と考えづらく、依然、敬意を払わないような状況は変わっていないと思う。他の文化ジャンルが開会式までにここまで破滅的な扱いとなり、一斉に自己言及を余儀なくされているなかで、ビデオゲームが良い状況でい続けられるなんてことはありえるのか?
エンブレム問題から現在までの6年間で、五輪型キャンセルカルチャーや政府・運営側の混乱、あらゆるポピュラーカルチャーのジャンルなどが複合し、五輪開会式にて文化的荒涼が具体化した風景を生み出した。
57年ぶりの五輪開会式がリミックスしたのは、半世紀にわたり進化した日本の文化状況ではなく、西欧社会が日本を評価しているクリシェを日本自身が内面化した、退行したオリエンタリズムが断片的に入りこんだ陰惨な姿だった。その光景は、持たざる一切のものを求めて、持てる一切のものを失ったものだった。
++++
トップ画像 by 葛西祝