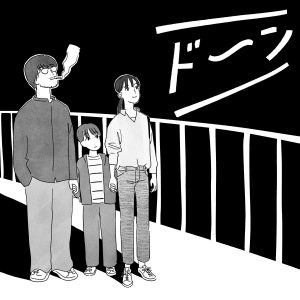(by 葛西祝)
若さを良いものと評することは多い。選手が全盛期を迎える期間が限られたスポーツはまさにそうだし、流行りのファッションや音楽からは誰でも良い意味で若さを捉えているだろう。
だけど多くの人が見て、若さがすぐに気づかれない分野がある。それがテキストにおける若さである。
毎日誰もが目にする文章には、まちがいなく若さとそれ以外がある。自分が30代を過ぎて半ばを迎え、これから年を重ねていくにあたってひとつ決めたことがある。「そろそろテキストで、事実を事実のままに書けるようにしよう」
当たり前に思えるが、なかなかできないことでもある。ちょうど30代を迎えたころ、あらためてテキストの書き方を考えなおす機会があった。自分の環境が変わり、本格的にテキストを書くことを仕事にしていくときだった。書き方を学び直し、考え直すなか、それ以前のブログでやっていたようなアプローチは、あまり良くない若さが目立っていたと思うようになった。
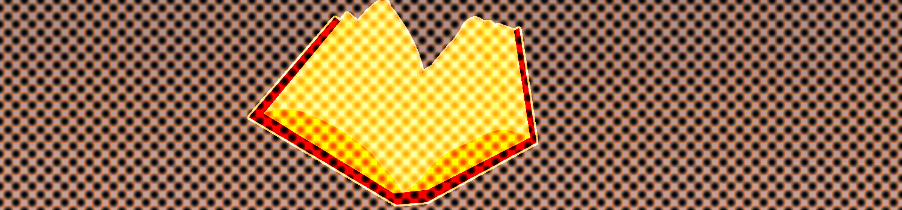
たとえば自分が書いた少し昔のテキストを読み返したとき、誰でも気恥ずかしさや足りなさを覚えることはあるだろう。
シンプルにテキストのロジックをまとめられていないことや、感情のままに書きつけるようなことも挙げられるが、ここで取り上げたいのは、逆に “とてもテキストを書ける人 ”ゆえに起こりやすい “若さ”の問題だ。
問題とはこうだ。見えている事実を、事実以上に大きなテーマで解釈し、哲学を引用してしまうみたいに衒学的な言葉で語り、飛躍してゆくようなことだ。これがテキストをそれなりに書ける人にしばしば見られることである。
ちょうどテキストにおける若さを考えていたとき、株式会社ゲンロンの取締役で批評家の東浩紀氏がnoteに掲載した、読者の質問を興味深い回答をしているテキストを読んだ。そこでは、まさしくテキストにおける若さがどういうことかをうまく言葉にしているように思った。
回答は「現代思想」とテーマを絞っている。だけど、学生くらい若いときから自分なりのテキストを書き続けている人が陥りやすい “若さ”が正しく指摘されている。
「事実以上に衒学的な言葉で語り、飛躍してしまう」ような “若い”テキストがどういうことか、ここでは東氏自身が20代のころに書いた批評を例に説明していると思う。「いまから振り返れば、自分のまわりに生硬な言葉で壁を作り、現実の他者を等身大で受け取らないようにしている弱さの現れでしかありません」と、当時の “若い”テキストを厳しく振り返っている。
この回答は見方を変えれば、多くの若さについてを指摘できるように思える。ファッションでも音楽でも、あるいは不良が威圧的な見た目をとるような若さのほとんどは、「等身大の現実を受け入れない」ことで、その華やかさのほとんどは自分の周りに生硬な壁を作るのに等しい。
とはいえポピュラーカルチャーや不良たちから見える若さというのは、はっきりと誰にでも見えているものだし、本人だってうすうすと自分の若さに気づいているものだ。だから20代から30代を過ぎたある時期から、若さが浅はかなものだと気づき、手を切ることが多い。
しかしテキストにおいては、他人はもちろん、書いている本人でさえも若さに気づきにくい。たとえばある事実を、必要以上に哲学や思想を織り込んだ語り口は、よほどうまくやらない限りは、貧弱な不良が特攻服を着込んで周りを威圧しているのと変わりない。
だけど衒学的な意匠や過度に文学風味の書き方を、すぐに特攻服に編み込まれた刺繍のようなものだと気づくことは難しい。
特攻服はいつまでも着ているわけじゃなく、若さが過ぎたとき、いずれ棚の奥にしまわれるのはわかるだろう。でもテキストにおける若さは、本人も他人も気づきにくいだけに長引く。結局のところ、そこに気づくのは同じようにテキストにおける若さを通りすぎた人なのかもしれない。

古い作家たちを紐解けば、テキストにおける若さについて考えさせるエッセイがいくつか見当たる。
三島由紀夫が『若きサムライのために』に収録した「文弱の徒」では、文学を志向することが現実とは関係のない安全地帯に逃げ込むことだと厳しく語る。彼自身が若いころに、戦時中で文学を否定されたことから、反抗するように文学へとのめりこむようになったという。
しかし年を重ねて、「まさか自分がそれを指摘するようになるとは思わなかった」と前置きしながら、「文学にモラルや生きる目的を見出そうとしている人たちが知らず知らず陥ってゆく罠」について批判していく。
郵便局員として働きながら、詩や小説を執筆したチャールズ・ブコウスキーも、若いテキストにうんざりさせられるエッセイを『死をポケットに入れて』に残している。詩を志す青年たちとやり取りしたところ、ブコウスキーはその浅はかな内容にうんざりとしてしまう。青年たちと自分を比べ、郵便局員として働きながら詩作に取り組んでいたことが、そんな浅はかさと距離を取ることができた一因だったと語っている。
いずれも、純粋に作家や批評家ひとつを自分の活動としていない人たちの指摘ではある。なんらかの形で “若い”テキストがどういうことかが分かると思う。
必要以上の衒学的な言葉も、極端なファッションのような若さにすぎないことに気づき、簡潔な言葉で書くように変わっていく人は変わってゆく。テキストでは若さも老いもすぐにわからないけれど、見えている人には見えている。
++++
イラスト by 葛西祝