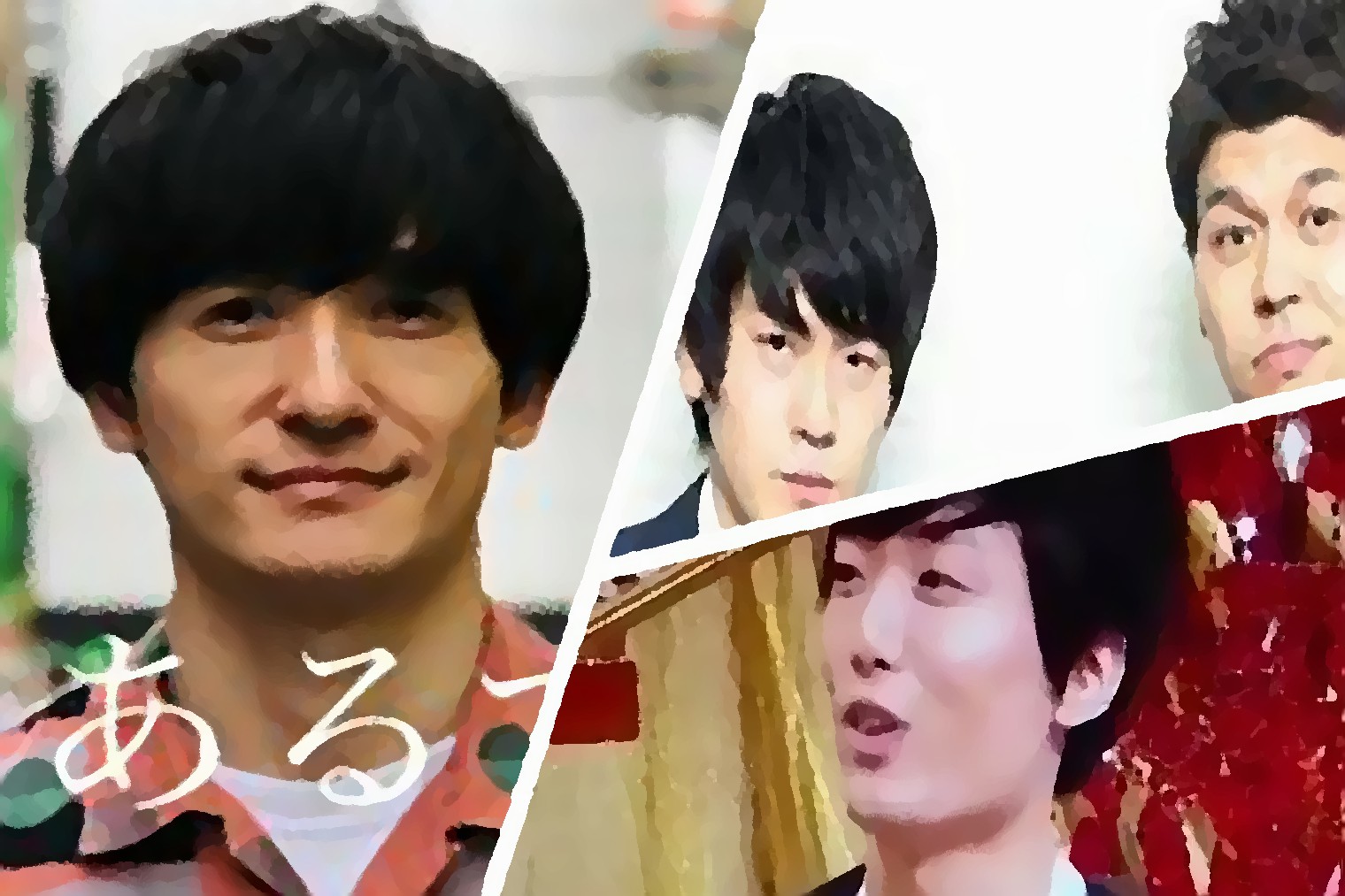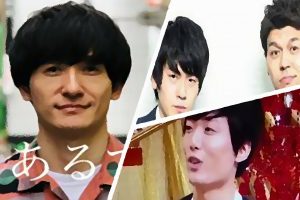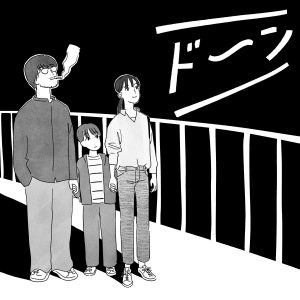インスタグラムやってますか。映え、してますか。
正直、インスタグラムは毎日開くものの、友人の近況をじっくり見ることはない。検索するのはもっぱら「おもしろいお笑いネタあがってないかな?」という気持ちから。つまり、駆け出しの若手芸人の発掘ツール。
今、若手芸人のネタ見せの場所にインスタグラムが使われている。インスタグラム、通称インスタはオシャレに敏感な女の子が充実した生活を記録する場から、お笑い芸人が自作のネタを表現する場という新しい形で普及し始めている。
人気を誇るのは、人物描写を得意とするピン芸人たつろう。「友達んちの冷蔵庫の残り物で何か作ろうとする奴」、「オススメ聞いといて頼まない奴」など、日常の「あるある」をモノマネする動画をアップしている。スカした若者の芝居や気まずい状況の描写が巧く、彼のフォロワーの中にはたつろうを真似た動画の投稿も目立つ。自らのあるある動画を「うるせーやつら」とシリーズ化しているのもブランディングの工夫の一つだ。
お笑いコンビ「土佐兄弟」の弟、勇輝も高校生モノマネで一気にフォロワーが伸びた。「先輩の学年の教室で無茶なギャグやらされる運動部の後輩」など、インスタユーザーの多い学生世代の好みにマッチしたネタが頻繁に更新される。人の言動や容姿をばかにする笑いではなく、男子高校生特有の「幼さ」を笑うという新しいジャンルである。
インスタグラムであれば、テレビに出ることのない無名の芸人でも60秒以内の短いネタを自ら発信することができる。撮影・編集し、BGMをつけ、テロップをつける。カメラワークも意のままに。そんな「持ちネタ動画」が連なるホーム画面は、いわば彼らにとって渾身のポートフォリオ(作品集)となっている。
若手芸人が自発的にネット上にネタをあげることによって、大きく変わったことがある。
ひとつは「知られる順番」。テレビに出たものが一般人に知られていくのではなく、一般人が見て笑うものがテレビに呼ばれるようになった。
先述のたつろうがフジテレビの人気番組「細かすぎて伝わらないモノマネ選手権」にて優勝したとき、披露したのはインスタで多くのイイネを集めた鉄板ネタ「たばこ買う時のど自慢みたいになる奴」だった。
もうひとつは「コラボの可能性」。代表的なのはお笑いコンビ「THE GREATEST HITS」の三戸キャップだ。インスタでメンタリストDAIGOのモノマネ動画をアップしたことをきっかけに、DAIGO本人とのコラボが実現した(しかもそのコラボ動画をyoutubeチャンネルにフルバージョンで公開し、インスタから視聴者を誘導しているのもさすがである)。
三戸キャップとDAIGOでは知名度の差が大きいことは明らか。それでもコラボ動画が実現したのは、テレビという媒体や事務所を介することのない「個々が知り合うプラットフォーム」が、ネットに確立されているから。発信者と発信者の出会いから生まれる可能性は無限大だ。
「お笑い」は進化する。それと同時に「お笑い」を発信する方法も進化するのは、むしろ自然といえる。アイディアを込めたたったの60秒で視聴者の心を掴む、自由度の高いツール。次世代のお笑いを担う若手芸人のこれからに必要なのは、オーディションという闘いの場ではなくインスタグラムという表現の場なのかもしれない。